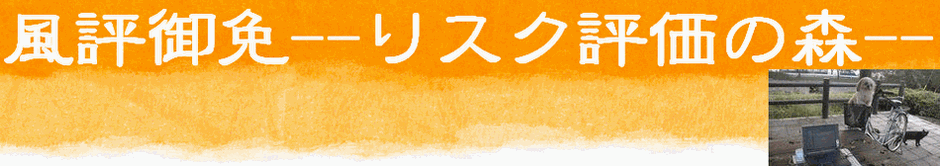「リスク評価」論への戸惑い・翻弄
「リスク評価」の研究の中間報告めいたものをというリクエストだが、とてもそんなものは書けない。なぜなら、法律家にとってリスク評価は躓きの石みたいなもので、この間、戸惑いと途方に暮れることばかりだから。以下、その戸惑いについて報告したい。
法律家が「リスク評価」に躓くのは1つには、それが科学に基づくものだからだろう。というのは、法律は何を隠そう、世の中の多種多様な専門分野の中でも最も科学から遠ざかった分野だから。文学でさえ、ピアジェの構造主義やチョムスキーの生成文法、ヤコブソンの構造主義的言語学などの一流の科学的研究の成果を踏まえているのに、法律にはそれすらない(構造主義的法律学すらまだ登場していない。その昔、川島武宜が「科学としての法律学」に挑戦したが、それも彼だけで途切れてしまった)。この夏、法律の最先端分野と言われる特許法を精読したが、発明の機械的、形式的な把握の仕方というレベルの低さに唖然とした。こんな機械的な発想では、最先端の科学や技術の成果である発明の本質にとても肉薄できないだろう、それができないようではいくら法律的な議論を深めていったところで不毛でしかない、と法律の先行きを考えて暗澹たる気持ちにすらなった。
もう1つ、私には個人的な思い込みがあって科学に躓く傾向があった――科学とはもともといかがわしいものである、と。小学校3年生のとき、クラスの女の子から「1+1は?」というトンチクイズを出され、「2だ」と答えると、彼女に「ブブゥ、残念でした。答えは1です」きょとんとする私に向かって彼女は言い放った。「だって、1個の粘土にもう1個の粘土を足してごらん。粘土は1個よ」これ以上完璧な答えはなかった。私は言葉を失った。以来、学校で教える科学と称する学問は、それは単にテストで○をもらうための方便でしかなく、科学は真理とは無縁のものであるというのが私のひそかな確信となった。
しかし、にもかかわらず、私は、現在、科学以上に信頼を置いている分野はない。それは、科学が時と場合によっていかにいかがわしさと隣合せのものであろうが、それがいかにまだ未解明なものを数多く抱えていようが、要するに、ごまんと様々な欠点を抱えていようが、にもかかわらず、それらを上回るただ1つの長所を持っていると思えるからだ。それが証明である。つまり、或る命題が証明されていない限り、科学はその命題の存在を主張することは許されないとしていることだ。それは権威や多数決を否定することである。そのことを教えてくれたのが数学者遠山啓であり、言語学者チョムスキーだった。遠山啓によれば、直角三角形に関するピタゴラスの定理は、経験的には古代エジプトで明らかであったが、古代ギリシャが要求したものは、それを真実であると主張するためには証明することであった。古代エジプトのように、王の権威でもってこれを真実とせよと命ずることを認めなかった。あくまでも証明が求められ、その結果、どこの馬の骨か分からないような人物(ピタゴラス)でも、それを証明し得た以上、受け入れられた。
この証明の精神こそ、過去、現在、未来にわたり科学が信頼を持ち得る殆ど唯一の基準のように思える。
ところが、今はやりの「リスク評価」は、この証明精神を骨抜きにするための、いかがわしさに満ち溢れているのではないかと思うことがある。なぜなら、証明とは、本来、或る命題を積極的に証明することであるのに対し、その反対の命題が証明されていないことを持って、こと足れりとするようなロジックがまかり通っているからだ。例えば、遺伝子組換え生物が外界に及ぼす危険性について、本来であれば、「そのような危険性がないこと」について証明してみせるのが科学である。しかし、世の中で往々にまかり通っているのは、上の命題の反対の命題「そのような危険性があること」を持ち出して、その命題を根拠づけるデータが今のところ示されていないことをもって、「そのような危険性があること」は今のところ証明されていない、だから、「そのような危険性がないこと」と考えてよいという結論、或いはそのような結論を前提にした対策が導かれていることである。これは、あたかもピタゴラスの定理について、「直角三角形の2辺の2乗の和は、斜辺の2乗にひとしい」とは限らないという命題が今のところ証明されていない以上、「直角三角形の2辺の2乗の和は、斜辺の2乗にひとしい」という命題が証明されたと考えてよいというのと同様である。
これはインチキではないか。なぜなら、証明とは元来、その命題を積極的に証明することであって、その反対命題を成立しないことを暫定的、消極的に示しただけでは足りないのは明らかだからだ。
しかし、こうしたインチキが堂々とまかり通っているのを見ると、これは確信犯ではないかとすら思う。つまり、「リスク評価」は科学に基づく必要はなく、単に科学に基づいているように見せかけることができさえすればよいのだ、と。言い換えれば、「リスク評価」は偽装科学が活躍する舞台だ、と。
しかし、これは何も特別なことではない。マキアヴェベリは、君主論で、君主は聖人である必要はないが、そう見える必要があるということを言っている。それと同じことだからだ。つまり、「リスク評価」もまた科学に基づく必要がないが、そう見える必要がある、そして、それ以上でもそれ以下でもない、と。
だから、「リスク評価」は本質的に「政治」の領域の問題である。もっと言えば、マキアヴェベリの君主論が、いかにして大衆の指示を獲得するかという「広告」の問題であるのと同様、「リスク評価」もまた、いかにして大衆の指示を獲得するかという「広告」の問題である。
それゆえ、「リスク評価」を有効に分析し、批判するためには、科学者や法律家というより、マキアヴェベリのような冷徹な政治批評家や広告批評家の才能と力量が求められる。もちろん、この指摘自体が、現在「リスク評価」を推進している人たちにとって容認しがたいことだろう。しかし、今まず必要なことは、「リスク評価」のやり方はいかにあるべきかを問うことではなく、現在進行中の「リスク評価」の正体の科学的分析である。それが適正に科学的に分析されれば、そこで、きっと「政治」であり、「広告」であることが明らかにされるであろう。
つまり、まずは、「リスク評価」が科学であることをまとった「政治」であり、「広告」であることことを知らせないことを止めて、科学であることをまとった「政治」であり、「広告」であることことを科学的に証明した上で情報公開すべきである。
その上で、科学であることをまとった「政治」であり、「広告」である「リスク評価」を、では、どうしたら、よりまともな「政治」であり、「広告」として機能し得るようになるのか、という課題に初めて正面から取り組むことが可能になるだろう。ここでもまた、私は、科学的精神のエッセンスである「証明」が最大の武器になり得ると思う。但し、今度は、「リスク評価」が対象としている遺伝子組換え生物といった不確実な現象だけではなく、それらの開発をめぐる有象無象の利害関係人の利害衝突という魑魅魍魎とした不可解な現象の「証明」である。その意味で、科学的精神の「証明」が活躍する出番はまだまだ無尽蔵にあり、新たなに「政治」の科学者、「広告」の科学者の出番も無尽蔵にある。この意味で、法律家の私に「法律」の科学者として何ができるのか、「リスク評価」を通じて、突き付けられ続けている。