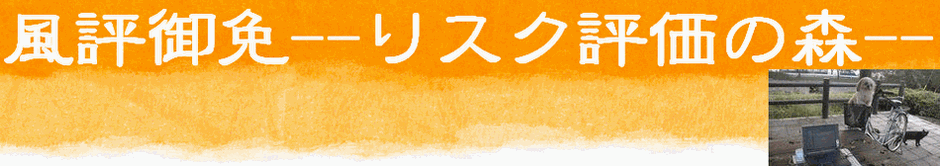皆さんへ
こんにちわ、柳原です。
昨日、上越で4月の市民法廷第1回準備会と記者会見をやりました。
準備会には、原告の山田さん、青木さん、佐藤さん、天明さん、プロデューサーの小山さんと私。
そこに、途中、朝日、日報、上越タイムスの記者が来て記者会見を実施。
最初、なぜ、市民法廷をやるのか、その抱負を私から述べ、それに対して皆さんから感想、意見を聞きました。皆さんとの間で、なかなか活発な意見の交流ができまして、私としては大変勇気づけられました。
ちなみに、新潟水俣病裁判では、一審のあと、控訴するかをめぐって原告の皆さんは疲弊して、これ以上もう無理だというので、控訴を断念しました。
それからすれば、イネ裁判でも、一審も負け、控訴も負け、さらに市民法廷をやるなんて、もういい加減にして欲しい、疲れたよという声が出てもおかしくないのに、皆さん、意気軒昂でした。これはなぜでしょう。
やっぱり、とりわけ二審の審理最終日で、裁判長の、カダフィー顔負けの強引な幕引きに、皆さんの怒りが収まらず、「正義の裁きを!」という声になったのだと思いました。
だから、市民法廷では、真相解明に蓋をした現実の裁判の報告と、同時に現実の裁判に代えて「正義の裁きを!」に取り組みたいと思いました。
その積りで、このあと、具体的な準備をしたいと思います。
準備会では、著作権裁判でシナリオの事件をやってきた私にシナリオを書くように要請がありまして、受けることになりました。
その際、1年半前の2009年夏の新潟集会(※)での失敗(シナリオ完成が集会前日と余りに遅い!)を踏まえて、今回は早めの完成(3月14日)をめざします。
(※)遺伝子組み換えイネの裁判判決を前に 市民へ、世界へ、すべての人へ 新潟集会
――イネ裁判が何であったのか、市民自身の視点で自己吟味する集会――
そのあと、3回、リハーサルを開き完璧を期し、4月9日の本番に備える。
昨日の準備会に参加して、4月9日の市民法廷は私にとって、この6年間のイネ裁判の集大成になるばかりか、生涯の転換点になるだろうという予感に教われました。
昔、エイドリアン・ラインという監督の「ジェイコブス・ラダー」(旧約聖書創世記の「ヤコブの梯子」という意味)を観たとき、我々人間が経験したことの意味を理解するためには、少なくとも2回、同じことを経験する必要があるのではないか、それは人間にとっての真理ではないかと思いました。この映画では、ベトナム戦争で犬死した兵士が、自分がなぜ犬死したのか、その意味を理解するために、もう1度死ぬ目に遭わされる、という映画です。
人類は、世界大戦を2度やらかした、1度では済まず、2度までもやり、2回目でこんなことを続けたら人類は絶滅すると初めて悟って、世界大戦の回避のために国際連盟を強化し、世界人権宣言を決議し、日本国憲法に戦争放棄を刻ませた。
実際はすぐさま東西冷戦に入り、いつでも世界大戦になってもおかしくなかったのに(実際、キューバ危機で人類は絶滅の瀬戸際まで行った)、世界戦争にならなかったのは、ひとえに2回の経験で人類が世界戦争の意味を学んだからですね。
だから、今、中東で起きた民衆の抗議行動を見ていて思うことは、これは2回目の市民革命なのだ、目の前の広がる出来事を眺めていて、ようやく、過去の1回目の市民革命がどういうものだったのかを初めて理解することができるのだ、と。
つまり、最初の市民革命のフランス革命とは何であったのか、ロシア革命とは何であったのか、ということです。
それと同じ意味で、今度の市民法廷は、2度目の法廷です、1度目が国営法廷に対する。
この2度目の法廷を経験することを通じて、きっと、1度目が国営法廷の意味が初めて明らかになる筈だと。
その積りで、今度の市民法廷に立ち向かいたいと思います。
その際、私が、この市民法廷で証明したいと思っていることが少なくとも2つあります。
1つは、私たちはもし事前に「然るべき準備と備え」をしていれば、2005年6月の野外実験の田植えを中止に追い込むことは可能だった。その「然るべき準備と備え」とは何かを示すこと。
もう1つは、私たちはもし国営法廷で、(事実論はそのままで)、別の法律論を立てていれば、裁判所は我々を負かすことはできなかった。その法律論が存在したのではないか。だとしたら、その「法律論」とは何か。
私は、別に痛恨の思いでこれを書いているわけではありません。
しかし、歴史は、将来、必ず、2回目の遺伝子組換え技術の裁判を登場させるでしょう。そのとき、これらを行使して、ムバラクを退陣に追い込んだように、チュニジアの大統領を亡命させたように、成果を上げなかったら、その時には痛恨の極みです。なんで、2度、(市民)法廷をやったんだ、と。それは将来、二度と同じ過ち、失敗を繰り返さないためだろう、からです。
その積りで、皆さんと歴史を刻んでいきたいと思っています。
よろしく。
-------------------------------------------
法律家 柳原敏夫(Toshio Yanagihara)
E-mail noam@m6.dion.ne.jp
GMイネ野外実験の差止訴訟「禁断の科学裁判」
公式サイト→http://ine-saiban.com/
------------------------------------------