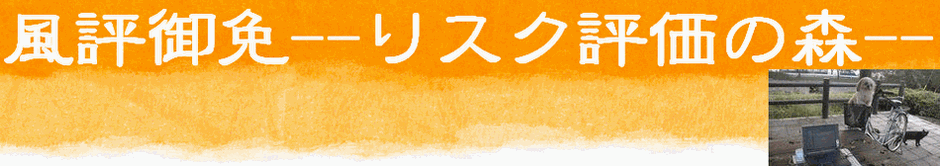市民の科学への不信はいかにして形成されるか(後半)
――「歪曲」されたリスク評価の事例の検討――
2010年11月30日
柳原敏夫
目次
はじめに――問題の分類――
第1部:古典的リスク評価の検討――事例検討――
第1部:古典的リスク評価の検討――事例検討――
第2部:現代型リスク評価の検討――理論検討――
1、序論
以上、「不確実な事態」といってもその危険性を科学的に予測することが可能なケースである古典型リスク評価の問題点を、事例に即して検討してきた。
これに対し、今後、さらに登場し、その適正な評価と対応をめぐって徹底した論議が必要となるのが、「不確実な事態」をその当時の科学水準に照らし、その危険性を科学的に予測することが不可能なケース、つまり現代型リスク評価である。
本来であれば、このタイプのリスク評価についても、本章でやったように、「生きたリスク評価論」を展開するために生きた事例の中から生きた教訓を汲み取る必要がある。しかし、現在の私には、それをするだけの準備がない。
そこで、以下、「死んだリスク評価論」に陥る危険を自覚しながらも、私がこれまで考えてきた現代型リスク評価の問題点を整理しておく。
2、問題の提起
現代型リスク評価のモデルケースは狂牛病(BSE)である。
日本は、狂牛病に感染した米国牛の発生を受け、2003年12月以来米国牛の輸入を停止していたが、2005年12月、2年ぶりに輸入を再開した。その根拠となったのが食品安全委員会の答申であるが、この答申の元になっているのが食品安全委員会の中に設置されているプリオン専門調査会がやった、米国牛の狂牛病に関するリスク評価である。ところで、このリスク評価をめぐっては、同調査会の座長代理(東京医大教授)が「国内対策の見直しを利用された責任を痛感している」と述べ、専門委員の辞意を表明するなどの不可解な事態が続発した。こうした出来事を目の当たりにすると、一方で、事実の科学的認識を職務とする科学者が政治的決定の行う役回りを演じているように見えたり、他方で、政治的決定を行うことを職務とする政治家・官僚が(自身の政治的決定に有利な)事実の科学的認識を行う役回りを演じているように見え、至るところで越権行為がまかり通っているように思える。
かつては、「神の権威」が政治統治に利用され、神のお告げに基づいて政治決定がなされたが(神政政治)、今日、それと同じ統治原理が科学の名のもとに行われているように見える。つまり、「科学の権威」が政治統治に利用され、神の代わりに科学のお告げに基づいて政治決定がなされている。しかし、かつて神政政治が政治の堕落を招いたように、科学の権威による統治も政治の堕落を招くのは必至である。それは上に紹介した、遺伝子組換えイネの事例を思い出せば一目瞭然である。ジャンク科学、似非科学が「科学の権威」の名のもとに政策決定の大義名分にされるからである。
2005年の米国牛輸入再開に至る一連のドタバタ騒ぎの経過を外側から眺めた市民は、赤裸々にさらされた「科学の権威」にすがる政治の姿というものを見て取ったのではないかと思う。その結果、市民の胸中に、たとえ真相は藪の中だとしても、政治と、そしてリスク評価と称する科学に対する不信感が一層形成されたことは間違いない。
しかし、このようなドタバタ劇は反復してはならない。そのためには、かつて、神政政治の弊害の反省から政教分離が確立したが、それと同様の政科分離=「政治と科学の分離」が科学でも必要である。
そこで、ドタバタ劇を反復しないために、そして、政科分離=「政治と科学の分離」に向けて歩みを一歩進めるために、一度、リスク評価の基本問題に立ち帰る必要がある。
3、リスク評価の基本問題
リスク評価の基本問題とは何か――それは、個別のリスク評価事例に対する不満・課題は鬱積しているにもかかわらず、何がリスク評価の本質的な課題であるかが依然さっぱり分からないことである。
通常、或る制度(システム)を制定するにあたっては、どんな制度を作るかをめぐって激しい価値観の対立・衝突があり、その調整が不可欠となる。その価値観は当然、その制度の運用に影を落とし、個々の運用場面での対立の原因となるからである。価値観の対立・衝突の吟味により制度の基本的な問題点は明快となる。もともと制度とはそういうものである。ところが、法律でメシを食っている者からみて信じ難いことだが、リスク評価はこれと全くちがう。リスク評価の基本的なあり方をめぐって根本的な価値観の対立・衝突がちっとも明らかにされない。さながら、リスク評価にはそのような対立は存在しない完全調和の世界のようにさえ思えてくる。
そうだとしたらそれは欺瞞である。現実に無対立な制度・システムなど原理的にあり得ないものだから。
以下、常々取り沙汰されることのないリスク評価のこの基本問題を検討する。
4、リスク評価とは何か<その1>
リスク評価とはなにか。この単純な問いに正面から答え得た者はまだ誰もいないと思う。なぜなら、少なくとも食品事故や生物災害について、リスク評価が取り沙汰されたのは狂牛病の出現などごく最近であり、個別事例への対応に追われる余り、自分たちが一体何をやっているのか、自省する余裕もその気もなかっただろうから。しかし、世の中には「解き方」を間違えたために、どうしても解けない問題というものがある。例えば、数学史の有名な出来事として五次方程式の解法。
x5+2x4+3x3+4x2+5x+6=0
このような五次以上の方程式は加減乗除の方法で解くことが(一般には)できないことは1824年、アーベルの手で初めて証明されたが、それまで数百年にわたって、これを加減乗除の方法で解けると信じた者たちにより空しい努力が積み重ねられてきた。この数学研究者の迷妄の歴史をここで想起しておくことは価値あることである。
5、リスク評価とは何か<その2>
しかも、この迷妄は「科学」内部の問題にとどまらない。
「芸術」と「法律」が交錯する裁判として有名な「悪徳の栄え」事件――1961年、フランスの作家マルキ・ド・サドの『悪徳の栄え』を翻訳し、出版した翻訳者の澁澤龍彦と出版社が、同書に性描写が含まれており、わいせつ文書に該当するとして起訴された事件だが、澁澤らは、「芸術性と猥褻性とは別次元の概念である」を前提にして、同書の芸術性には理解を示さず、専ら善(法律)の次元で判断しようとした検察に反発する余り、「芸術性と猥褻性とは別次元の概念ではなく、芸術性が高い作品ではその芸術性により猥褻性が消失することがある」という論理でもって対抗しようとした。つまり、美的判断が法的判断に優先するという立場を取った。しかし、この「解き方」は裁判所に容易に理解されず、解き方をめぐって「永遠の水掛け論」に陥り、その中で澁澤は不貞腐れ、さじを投げ出してしまった。
しかし、彼の提起した問題は少しも解決されていない。時を経て同じ問題が反復される運命にある。その一例が1994年に提訴された「石に泳ぐ魚」事件である。ここでもまた、芸術性という美的判断がプライバシー保護という法的判断に優先するという主張が反復された。このような芸術裁判で、その「解き方」をめぐって美(芸術)と善(法律)の判断の関係が問われているが、その正しい「解き方」が分からないため迷妄が反復されている[1]
6、リスク評価とは何か<その3>
他方、この迷妄は別に専門的、特別なことではなく、日常の出来事、例えば教育現場などでも登場する。かつて、日本で最も自由な教育を行なうと宣言し、斬新な芸術教育で注目を集めた某私立学校で、その後、悪質ないじめや校内暴力が発生し、大量の学生を退学処分したとき、みずから設立理念を否定するような処分行為に出た学校関係者は途方に暮れたが、その学校を訪れた柄谷行人はこう言った――いくら自由と自立を尊重するという理想的な教育をしても、いじめや暴力は決してなくならない。もともとそれは人間の攻撃性に由来するものだからです。そこで必要なのは、芸術(音楽、美術、文学)ではなく、むしろ人間の攻撃性を科学的に解明しようとしたフロイトです。いじめや暴力に対してまず必要なのは、美的判断でも倫理的判断でもなくて、科学的判断(認識)だからです、と。
つまり、いじめや校内暴力に対しては、正しくは、まず真(科学)で立ち向かうべきなのに、解き方を間違って、美(音楽、美術、文学といった芸術)や善(倫理)で解こうとしたために、迷妄に陥ったのだ、と。
7、リスク評価とは何か<その4>
しかし、これらはリスク評価にとって対岸の火事ではない。これと同じ迷妄にリスク評価もまたさらされているからである。
食品安全委員会などの公式的見解によれば、リスク評価とはあくまでも科学的な判断であるという立場、つまり真(認識)だけで問題を解こうとするものである。しかし、果してそうだろうか。食品安全委員会の現実のリスク評価の混迷ぶりを見ていると、「解き方」を間違えていないだろうか。
そもそもリスク評価が最も問題となるのは、測定値が科学的に正しいかどうかといったことではなく、むしろ、そうした科学の探求を尽くしてみたが、それでもなお或る現象の危険性について確実な判断が得られないときである。つまり、科学の力が尽きたところで、初めて、ではこの「不確実な事態」をどう評価するのだ?という判断が問われる時である。その意味で、リスク評価とは科学の問題ではなく、科学の限界の問題である。言い換えれば、リスク評価とは、科学的に「解くことができない」にもかかわらず「解かねばならない」、この2つの要求を同時に満たす解を見つけ出すというアンチノミー(二律背反)の問題である。
そうだとしたら、このアンチノミーをどうして科学的判断=真(認識)だけで解くことができるだろうか。科学の限界の問題を科学で解こうとすることほど非科学的なことはないからである。
8、リスク評価とは何か<その5>
しかし、そんなことは食品安全委員会などの頭のいい人たちはとっくに分かっている筈である。けれど、彼等の使命は科学的に「解くことができない」問題を同時に「解かねばならない」ことにある。となれば、さしあたり、科学の限界の問題にもかかわらず、さも科学の範囲内の問題であるかのように振舞って解くしか手はないだろう、たとえそれがどんなにいかがわしく、欺瞞的に思われようとも。
これが今日の現代型リスク評価を覆っている迷妄の正体であり、市民に対して科学に対する癒し難い不信感を形成させる原因でもある。
9、リスク評価の迷妄の打破のために
では、リスク評価のこの迷妄を打破する道はどこにあるだろうか。それは別に難しいことではない――リスク評価の方法という問題に科学の光を照射するだけのことだから。つまり、科学としてのリスク評価方法を確立することである。その際のキーワードは、科学史として言い古されありふれたものだが、真実に対する正直と勇気、この2つで十分だと思う。すなわち、
第1に、問われている現象のリスク評価に対して、自ら科学の限界にあることを率直に認める勇気を持つこと。
なぜなら、もともとリスク評価の本質とは科学の限界の問題なのだから。
第2に、真(認識)における「科学の限界」を踏まえて、善(倫理・法律)と美(快・不快)の判断を導入して、それらを総合して判断する勇気を持つこと。
なぜなら、哲学者カントによれば、我々が世界を見、物事を判断するとき、①真(認識)、②善(倫理・法律)、③美(快・不快)という異なる独自の3つの次元の判断を持つが、リスク評価が①において科学の限界に直面し、科学的に「解くことができない」以上、これを踏まえて②と③の2つの次元の判断を導入して解くだけのことである。それが科学的に「解くことができない」と同時に実践的に「解かねばならない」アンチノミーの正しい「解き方」である。
10、リスク評価論の外<芸術裁判の躓きその1>
以上の通り、科学の限界の問題であることを本質とし、科学本来の領域=真(認識)だけでは太刀打ちできないリスク評価のあり方をより理解するためには、一度、リスク評価論の外に出る必要がある。
四年前、最高裁に絵画(模写)をめぐる芸術裁判の書面を提出した[2]。これは一市民の現在の裁判制度に対する徹底した不信を表明したものである。その真髄は次の通りだ――模写とは絵をそっくりに写し取ることである。だから、原画と似ているのは当然である。だが、本当にそれだけだろうか。似ているで、おしまいだろうか。果してそれに尽きるだろうか。なぜなら、光琳、大観、ゴッホ、彼らのどんな精密な模写といえども、そこには必ず原画との「ちがい」が認められるが、このちがいを当然のこととして「取るに足りない些細なちがい」とは評価できない筈だからである。そうだとしたら、いったい、いかなる場合なら「取るに足りない些細なちがい」として無視することができるのだろうか――この原告の根本的な疑問に対し、裁判所は何ひとつ答えることなく、何ら判断基準を示すことなく、単なる印象でもって原告の主張を斥けた。これでは「法(判断基準)による裁判」の放棄である。申立人が上告した根本理由は一審、二審裁判所の「逃げる司法」に対して、最高裁に「逃げない司法」判断を求めるためである。
だが、私自身、まだよく分らないことがある。それは――裁判所は一体どこからどこに逃げているのだろうか。イデオロギー裁判でもない芸術裁判で、あれだけボロクソ追及されたにもかかわらず、なぜ彼らは逃げ続けるのだろうか。ところで、こうした逃走は何も裁判所に限ったことではなく、食品安全委員会でも同様なのではないのか。
11、リスク評価論の外<芸術裁判の躓きその2>
では、裁判所は、どこからどこへ逃亡したのか。この場合、美から善(倫理・法)へである。つまり、本来であれば、裁判所は、まずは作品の適切な美的判断に向かうべきであった。それを終えてのち初めて、作品の法的な判断に進むことができる。しかし、裁判所は厳密な美的判断を何ひとつしなかった。それをしないでいきなり法的判断に出たのである。それが印象による判断と見えたのは当然である。だから、私は次のように批判するしかなかった。
《通常の裁判と比較し、芸術裁判の大きな特色は、裁判の対象が通常の事実認識(認識的判断)だけでは済まず、芸術裁判の対象である芸術作品を正しく把握するためには適正な美的判断が不可欠だということである。それが、古来、著作権事件のみならず著作権以外の様々な芸術裁判(「チャタレー」事件、「悪徳の栄え」事件など)の審理を著しく困難なものにした2)。しかし、裁判制度が芸術を法廷に持ち込むことを認める以上、「適正な美的判断」という課題は回避しようがない(それは、科学が法廷に持ち込まれる以上、「適正な認識的判断」という課題は回避しようがないのと同様である)。裁判所が適正な芸術裁判を実施し、文化の発展に寄与するためには、この厳格な適用が不可避である。
以上の芸術裁判における特色を標語的に言えば、次のようになる。
――美のことはまず美に聞け。それから、善の判断に進め、と。》
しかも、裁判所のこの迷走は今に始まったことではない。1875年、日本の裁判制度が始まって以来今日まで続いている。なぜなら、その迷走が自覚されたことは、ただの一度もなかったのだから。もっとも、それが顕在化したことはあった。「チャタレー事件」と「悪徳の栄え事件」である(1957年3月13日[3]と1969年10月15日[4]の最高裁判決)。しかし、このとき、芸術家の自由を守ろうとしたリベラル派裁判官は、「芸術性と猥褻性とは別異の次元に属する概念であり、両立し得ないものではない」の多数意見に反発する余り、「芸術性と猥褻性とは別次元の概念ではなく、芸術性が高い作品ではその芸術性により猥褻性が消失することがある」という論理でもって対抗しようとした(裁判官色川幸太郎など)。
芸術家の自由を最大限守ろうとしたリベラル派の動機は理解できる。だが、私には彼らの論理が気に入らない。彼らの論理だと――この作品は素晴らしい芸術的価値がある。だから、これを「猥褻」として処罰するのはおかしい、と。これは芸術を社会的倫理の上に置こうとする芸術至上主義である。だが、目的(芸術)は手段(倫理)を正当化し得るだろうか。そんなことはない。むろん芸術は最大限尊重されなければならない。だからといって、芸術だけが他と異なり、社会倫理から超越して存在する訳ではないからである。
そして、これと同じことが科学でも起きる。この論理を科学に当てはめると――この研究は素晴らしい科学的価値がある。だから、これを「危険」だからいって規制するのはおかしい、と。
リベラル派裁判官の弱点は多数意見の論理の粗雑さを見抜けなかったことにある。芸術性と猥褻性が次元が異なるのは多数意見の言う通りである。しかし、両者はそれだけで済むような単純な関係ではない。両者(美的判断と法的判断)の正しい関係はもっと複雑精妙であり、その正確な把握なしには最終的に適正な判断は導けない。
12、リスク評価論の外<芸術裁判の躓きその3>
では、美的判断と法的判断の正しい関係はどう考えたらよいか。さしあたり、哲学者カントにならって、次のように考えるのが適切だと思う。
A.我々が世界を見、物事を判断するとき、①真(認識的)、②善(道徳的)、③美(美的、快か不快か)という異なる独自の3つの次元の判断を持っている。
たとえば、「オウム真理教」がマスコミに登場した頃、彼らに対する評価は分裂したが、それは彼らを①「さっそうと出家してスタイルもカッコいい」といった美的に見るか、②その宗教的な教義や実践がいかなるものかという倫理的に見るか、③そのスタイルや宗教的教義にもかかわらず、実際にやっていることはインチキであり、犯罪ではないかという認識のレベルで見るかという違いに由来した。つまり、もともと我々の判断に美的、倫理的、認識的の3つの異なる次元の判断があることに由来するものだった。
B.この3つの次元の判断はおのおの他の次元の判断から独立して存在している。
映画や小説ではよく美形の犯罪者やヤクザが主人公として登場するが、それらに夢中になる観客は、鑑賞の間、倫理的判断とは別に、美的判断で鑑賞しているからである。だからといって、その観客が普段、犯罪者やヤクザに好意を抱いている訳ではない。彼らは、無意識のうちに、映画館の中と日常とで次元のちがう判断を行使している。
C.それゆえ、或る次元の判断を他の次元の判断をもって省略、代用、置きかえることはできない。
映画館で美形の犯罪者やヤクザに夢中になったからといって、その観客を倫理がもとるとは誰も非難しない。美的判断と倫理的判断とは元来別の判断であり、両者を混同すべきでないのだから。
D.にもかかわらず、この3つの判断の区別は、日常で必ずしも明確に自覚されているわけではなく、通常、この3つの次元は渾然と交じり合っている。
例えば、19世紀のフランスで、W. シェークスピアの「オセロ」を上演した際、悪役イアーゴの女房殺しの場面に憤激した観客が俳優を射殺した事件が発生したが、この悲劇は美的判断と倫理的判断とを区別できなかったためである。しかし、簡単にこの観客を笑うことはできない。我々もまた、例えば人を愛するとき、その理由は相手に②善(道徳的)の次元で人間的魅力があるからか、それとも③美(美的)の次元で美的、性的魅力があるからか、さらには両方ともあるからか、愛する本人にもよく分かっていないことが多いように、その区別は必ずしも容易ではないからである。
E.そのため、本来、或る次元の判断が求められるときに、誤って別の次元の判断でこと足れりとしてしまうことが往々にして起きる。
前述した通り、かつて自由な教育と斬新な芸術教育で注目を集めた某私立学校で悪質ないじめや校内暴力が発生した時、柄谷行人はこう言った――いくら自由と自立を尊重するという理想的な教育をしても、いじめや暴力は決してなくならない。もともとそれは人間の攻撃性に由来するものだからです。そこで必要なのは、芸術(音楽、美術、文学)ではなく、むしろ人間の攻撃性を科学的に解明しようとしたS. フロイトです。いじめや暴力に対してまず必要なのは、美的判断でも倫理的判断でもなくて、科学的判断(認識)だからです、と。
F.しかし、これらの3つの次元の判断をきちんと区別し、それらを自覚的に行なうためには、それ相当の文化的訓練が必要である。
フランスの美術家デュシャンが「泉」と題して便器を美術展に提示したとき、多くの者たちは眉をひそめ、狼狽したという。しかし、デュシャンは単に《芸術を芸術たらしめるものが何であるかをあらためて問うた》だけである5)。つまり、便器という対象に対し、認識的(①真)と倫理的(②善)関心を括弧に入れて見るという芸術本来の判断を求めたにすぎない。しかし、このことを理解するには、それ相当の文化的訓練が要る。
その意味で、もともと科学者もまた、こうした文化的訓練を積んだ者のことである。近代科学は、ガリレオに見られるように、研究の対象を、②善(道徳的、宗教的)的と③美(美的、快か不快か)的関心を括弧に入れて認識することにおいて成立したものだからである。この点で、医者も同様である――産婦人科医は、妊婦を美的或いは性的に見ることを括弧に入れる訓練を積んでいる5)。しかし、この訓練がきちんとできていないと、ときとして悲劇が発生する。例えば、外科医は、手術のとき、患者をたんなる手術の対象物として突き離して見る訓練を積んでいるが、身内が患者のような場合には、時として「相手が手術で苦しむのではないか」といった人間的感情を拭い去ることができず、メスの操作が狂うことがあるという。他方、未熟な外科医の場合、手術が終わったあとでは患者を生きた人間として見るべきなのに、依然、相手を物のように突き放してしか見られない[5]。
G.その上で、②善(法的判断)においては、①真(認識的判断)や③美(美的判断)を基礎とし、それに基づいて、善独自の判断を行なうという関係に立つ。いわば、善(法的判断)の判断の全体は、第一次的に①真(認識的判断)や③美(美的判断)を行ない、これを受けて、その次に②善(法的判断)を行なうという二重構造になっている。
その意味で、チャタレー事件と悪徳の栄え事件で適正な判断を下すためには、まずは美的判断(作品の芸術性など)を下し、その結果を踏まえて、次に法的判断(わいせつかどうか)に進むべきであった。「芸術性と猥褻性とは別次元の概念だから、芸術性の主張は猥褻性の判断に関係ない」で済むようなのんきな話ではない。それはちょうど、法律上の因果関係の判断において、事実的因果関係の判断(①真)を踏まえて、法的な判断(②善)を行うのと同様の困難さがある。例えば公害事件では、たとえ①真〔認識的判断〕につき、事実上の因果関係の立証が不十分であっても、②善〔法的判断〕においては、言われなき被害を蒙った被害者救済の観点から、ある程度以上の心証が得られた場合には、その得られた心証度の程度に応じて法的な因果関係を肯定するという独自の工夫をこらされることがある[6]。
13、リスク評価論の外<科学裁判の躓きその1>
以上のことは芸術裁判(美的判断と法的判断の関係)に限らない。科学裁判でも同様である。ここでは、認識しかも専門的分野の認識と法的判断との複雑精妙な関係が問われている。そのことを痛感したのは、本事例として紹介した本GMイネ裁判(仮処分手続)の2005年10月、二審の判断のときである。耐性菌問題に対し、一審裁判所は、申立人の危惧は「未だ証明がない」という慎重な事実認定だったのに対し、一審より短期間しか審理しなかった二審の裁判所は、相手方が科学的に公知の理由に基づき「ディフェンシンがイネの細胞から外部に出ないから耐性菌の出現の可能性は皆無である」と主張したのを全面的に採用し、原告市民やその協力者である研究者らの危惧は「杞憂」にすぎないと断じた[7]。しかし、実は、相手方の「ディフェンシンがイネの細胞から外部に出ない」という主張の根拠こそ、逆に科学的に公知の事実に基づき成立しないものであることが明らかなものだった10)。
これほどまで科学的に根拠薄弱な事実認定をいとも自信満々にやってのける裁判所を目の当たりにして、私は自問自答せざるを得なかった――この恐るべき過信はどこからくるのか、と。
思うに、1つは無知から来るのだろう。それは、前述した認識と法的判断の関係に関する無知である。恐らく、彼らには①真(認識的判断)と②善(法律的判断)の関係、両者の峻別とその関連性について明確な自覚はないだろう(そのことは、チャタレー事件最高裁判決の問題点が何であるか聞いてみれば一発で判明する)。①真(認識的判断)と②善(法律的判断)の峻別の必要性を自覚している者なら、どんなに困難に満ちたものであろうとも、専門的分野の徹底した認識に向かうことの重要性を自覚できる。なぜなら、この認識の次元でミスったら、どんな立派な法的判断を下したところで、取り返しのつかない結果になるからである。それは、事実として犯罪をやっていない者をやったと認定する冤罪を見れば一目瞭然である。
したがって、二審の裁判所は、事実関係は専門的でどうもよく分らないから適当なところで判断して、あとの法的判断も漫然と「まあ、いいか」と下したとしか思えない。というのは、裁判所は、すぐそのあとで、市民が指摘した「相手方は、野外実験の承認を得るにあたって、申請書に本来なら『コマツナのディフェンシン』と書くべきところを、偽って『カラシナのディフェンシン』と書いた。これは重大な違反である」という点について、市民の指摘した事実をあっさり認め「遺憾である」とまで言っておきながら、それに続けて、しかしその違法性の評価については「実験承認手続に重大な瑕疵があるとは評価できない」(13頁)と、なぜこれが重大な瑕疵にならないのか一言も理由を明らかにすることもなく法的判断を下したからである。しかし、これは遺伝・育種学や分子生物学のイロハを知る者にとって驚異=脅威である。たとえ同じアブラナ科の植物とはいえ、コマツナとカラシナではその遺伝子の配列は異なり、それゆえ、コマツナとカラシナのディフェンシンでは、いもち病菌等に対する作用も異なり、それゆえ、遺伝子組換え実験の安全性の確認についても、それぞれ別個独立に検証しなければならないもので、同じアブラナ科の植物だからどちらでもたいした違いはないと評価することなど思いも及ばないからである。これでは、コマツナをカラシナのディフェンシンと偽って記載した事実はないと必死に弁明した被告=本事例の研究者たちもきっと浮かばれないだろう。徹底した事実認識に向かうことの重要性を自覚しない人たちの手にかかると、こうした関係者全員に不幸な事態をもたらす。
14、リスク評価論の躓き
リスク評価論はこれら芸術裁判や科学裁判の喜悲劇を対岸の火事として済ますことはできない。その出火源は裁判(科学裁判・芸術裁判)もリスク評価も同一だからである。
つまり、リスク評価論でも、
(a) ①真(認識)と②善(道徳・法・実践)の両方の次元が存在し、(b) 一方をもって他方を省略したり、代用することはできず、必ず両方の判断を行なう必要があり、(c) おのおの判断においては、それ以外の次元(①真〔認識〕であれば、②善と③美。②善〔道徳・法・実践〕の次元であれば①真と③美)を括弧に入れて判断する必要があり、(d)、両者の関係については、①真〔認識〕の判断を基礎として、それに基づいて、次に②善〔道徳・法・実践〕独自の判断に進むという手順を取る必要がある。つまり、リスク評価とはこうした二重構造を持った善の判断の一つである。
ところで、①真(認識)の判断なら、その適正な判断のための文化的訓練を積んだ者=科学者がおり、③美の判断なら、その適正な判断のための文化的訓練を積んだ者=芸術家がいる。しかし、本質は②善(倫理・法・実践)の領域の判断である「リスク評価」について、上述の科学者や芸術家に匹敵するような、その適正な判断のために必要な文化的訓練を積んだ者はいるだろうか。
現在、リスク評価に関わる大部分の人たちは、リスク評価の対象となる分野の科学者、研究者たちである。しかし、彼らは①真(認識)の判断ならその適正な判断のための文化的訓練を積んだかもしれないが、②善(道徳的)の次元の判断については別に特別な訓練を受けてきた訳ではなく、素人同然の筈である。
ましてや、二重構造を持った善の判断において、最初の①真(認識的)の次元の検討で、その方面の専門家として判断を下しておきながら、引き続き、これとは独自の判断である②善(道徳的)の次元の検討で、善に関する文化的訓練も受けていない彼らに、①真(認識的)の関心を括弧に入れて、自ら下した認識的判断を引いた目で適正に判断することを期待できるだろか。実際は、最初の①真(認識的)の次元の検討で出した結論を、そのままズルズルと②善(道徳的)の次元の検討でも肯定してしまう可能性がかなり高い。なぜなら、最初に自分たち自身で検討して確信をもって導き出した認識的判断を、次の②善(道徳的)の検討において、これを否定することも含めて突き放して判断することは、そうした文化的訓練を受けたことがない人には、人性の本質上まず不可能であると言うほかないからである。その結果、このとき、彼らは、いわば善(倫理・法・実践)から真(認識)へ逃亡する恐れが高い。
さらに、リスク評価が実際に問題となる場面とは、そもそも科学の探求を尽くしてみたが、それでもなお危険性について確実な判断が得られなかったときである。つまり、科学の力が尽きたところで、初めてこの「不確実な事態」をどう評価するのかという判断が問われる時である。だから、リスク評価の場面とは厳密には科学の問題ではなく、科学の限界の問題である。その意味でも、科学者がリスク評価の判断者として相応しいとは限らない。科学の問題に通暁している専門家=科学者が必ずしも科学の限界の問題にも通暁しているとは限らないからである。
その意味で、リスク評価の判断者として相応しい人とは、科学というシステムの内部で優秀である科学者ではなくて、むしろ科学の限界といういわば「科学のメタレベルの問題」或いは数学基礎論に対応するようないわば「科学基礎論の問題」に通暁している者である。
では、②善(道徳的)の領域の専門家である法律家はどうだろうか。
確かに、法律家は②善(法的)の適正な判断のための文化的訓練を積んだ者である。しかし、すでに見た通り、20世紀までの法律家は、一般的、日常的な事実を前提にした②善(法的)の適正な判断の文化的訓練を積んでいるかもしれないが、いったん科学的、あるいは芸術的に専門的な事実になるや、その文化的訓練は発揮されないにひとしい。それは彼らが前述の文化的訓練の何たるかを殆ど自覚していないからである。だから、従来の法律家では科学的な専門的知見が前提となるリスク評価では使い物にならない。このとき、彼らは、前述の研究者たちとは反対に、真(認識)から善(倫理・法・実践)に逃亡するだろう。
15、科学の限界の不承認について
研究者・専門家の特徴の1つは、研究者同士の世界(いわば内部の世界)でなら正直に認めるのに、ひとたび食品安全委員会のような場(いわば外部の世界)になると、一転して、リスク評価において自分たちが「科学の限界」に直面していることを正直に認めようとしないことである(むろん2005年のプリオン専門調査会の調査委員のように、科学の限界を正直に認める見識と勇気を持つ研究者もいる)。その振るまい方は、かりそめにも「科学の限界」であることを認めようものなら、リスク評価のケリがそこで着いてしまうかのように思い込み、怖れている節すら感じられる(「科学としてのリスク評価」であれば、科学の限界はリスク評価のスタートであっても、決してゴールではないのに)。
そのため、彼等は自分たちは元々「科学の限界」には直面しておらず、科学の範囲内の問題として処理できるのだという(さながら魔法の)ロジックをひねり出す。そのロジックの1つが
「今までのところ、危険性を示すデータが検出されていない。だから、これは安全と考えてよい」
である。例えば、
①.上に紹介した遺伝子組換えイネの事例の裁判のケース
(1)、リスクの1つ、カラシナ・ディフェンシン耐性菌が出現する可能性について
「実際、耐性菌の出現についての報告もない」(被告)
「何か起きるのであれば、既にカラシナ畑で起こっている」(被告)
(2)、リスクの1つ、周辺の非組換えイネとの交雑防止のための隔離距離について
「これまでの知見では、交雑の生じた最長距離は25.5メートルである」(被告)
②.体細胞クローン牛技術のリスク評価書(2009年6月)
「体細胞クローン牛や豚、それらの後代(子供)の肉や乳について、栄養成分、小核試験、ラット及びマウスにおける亜急性・慢性毒性試験、アレルギー誘発性等について、従来の繁殖技術による食品と比較したところ、安全上、問題となる差異は認められていません」(食品安全委員会)。
すなわち、これらは危険性を示すデータが検出されないことを安全性を導き出す根拠にしている。しかし、検出されないことが果して安全性を導き出す合理的根拠たり得るだろうか。
そもそも近代科学において「データ」とはどうやって検出されるものなのだろうか。実はデータは見つかるものではなく、我々が見出すものである、それもしばしば、ベーコンの指摘の通り、自然を拷問にかけて自白させるやり方によって。
例えば、もしアインシュタインの一般相対性理論がなかったら、皆既日食で、太陽の近傍を通る星の光の曲がり方を示すデータは決して検出されることはなかったろう。むしろ、このデータは一般相対性理論によって初めて存在するに至ったのである(その詳細はH.コリンズほか「七つの科学事件ファイル」104頁以下参照)。また、10-21~10-23秒しか寿命がない素粒子の存在を証明するデータが自然に見つかることは凡そあり得ない。つまり、一般相対性理論や素粒子の科学的な仮説が先行し、なおかつその検証のために必要な実験装置が考案されて初めて、これらのデータが存在するに至るのである。
そうだとすれば、リスク評価においても、科学の限界のために、いかなる具体的な危険な事態が出現するかを予見できず、その具体的な危険性を検証するための実験装置も考案できない状況下で、その危険性を示すデータが存在するに至ることなど(危険な事態が現実化した場合以外に)凡そあり得ない。
これに対し、危険性を示すデータが検出されないことを安全性を導き出す根拠としてよいと説明するためのロジックとして使われるのが、問題の新技術は「従来技術の延長=実質的に同等にすぎない」から、或いは体細胞クローン技術は「(安全性が取り沙汰されている)遺伝子組換え技術は全く別物」だから、といったものである。
しかし、そもそも「従来技術の延長にすぎない」かどうかはリスク評価をしてみて初めて判明する結果なのに、それをリスク評価のための材料にするのは本末転倒である。また、従来技術の「延長=実質的に同等」かどうかは真(認識)の次元ではなく、価値判断の次元の事柄である。それを科学的検討を行なうと称する場で実施することは越権行為というほかない。
また、体細胞クローン技術について、DNAを組み込まれる立場(ここでは卵子)からすれば、一部のDNAを組み込まれるか(遺伝子組換え技術)、それとも核全部のDNAを組み込まれるか(体細胞クローン技術)という違いでしかない。丸ごとDNAを組み込むから、一部だけのDNAを組み込む遺伝子組換え技術とちがって安全だという科学的根拠はどこにもない。
16、善(倫理・法律)の判断とはどういうことか
善の判断とは一言で言って、価値観をめぐる判断である。現代社会は多様な価値観が共存する場だから、善の判断もまた、多様な価値観の衝突の調整ということになる。
ここで取り上げたいことは、「多様な価値観」の変容という問題である。今、それを時間と空間の2つの軸に沿って取り上げる。
(1)、時間軸をめぐる「多様な価値観」の変容
これまで法律・倫理が問題にして来た価値は、いまここで生きている人を対象にしてきた。
しかし、それでは不十分ではないかという問題提起がなされている。それが一方で、死者の問題(臓器移植をめぐる死の定義)、他方で、胎児の問題、さらには未だ生まれざる未来の人々の問題である。
なぜこれが取り上げられることになったかというと、科学とりわけ生命科学の進歩のおかげで、人間、胎児、未来の人の価値が損なわれる恐れという新たな事態が出現したためである。
(2)、空間軸をめぐる「多様な価値観」の変容
これまで法律・倫理が問題にして来た価値は、基本的に人及び人の集合(団体)を対象にしてきた。
しかし、今ではそれでは不十分ではないか、動物も人間と同等の価値を享受すべき存在であり、種が異なることを根拠に差別するのはおかしいという動物の権利が取り上げられるようになった。
そこで、体細胞クローン動物技術のリスク評価にあたっては、この動物への倫理という観点からも検討すべきである。
尤も、動物倫理の考え方として、動物が受ける「苦痛」に着目し、その苦痛を感じる能力に応じて人間と同等の価値を享受すべきであるという立場があるが、もしこれを倫理の根拠とするならば、倫理の対象は動物にとどまらない。植物でも微生物でも、彼らは悲鳴はあげないが、生命体である以上「苦痛」の可能性は否定できないからである。
例えば、DNAを大量コピーするためにDNAクローニングで、大腸菌に組換えプラスミドを進入させるためにリン酸カルシウムを加え、大腸菌の細胞壁を溶かし、あいた穴からプラスミドが浸入するようにするとき、それは大腸菌に「苦痛」を与えているのではないだろうか。
また、植物で遺伝子組換えをするために、DNAクローニングと同様、植物細胞に組換えプラスミドを進入させるために、植物の細胞壁をセルラーゼという酵素で破壊し取り除いてしまい、プラスミドがたやすく細胞内に浸入できるようにするとき、それは植物細胞に「苦痛」を与えているのではないだろうか[8]。或いは、植物で遺伝子組換えをするために、パーティクルガン法で、目的の遺伝子を結合させた微粒子を弾丸としてガンで植物細胞に撃ち込むとき、それは植物細胞に「苦痛」を与えているのではないだろうか。
これに対し、何を寝ぼけたことをと思うかもしれない。しかし、人類は少し前まで、肌の色がちがうというだけで相手を同等の人間と見ることができず、或いは非ヨーロッパ人というだけで、召使の彼らの前で平気で裸になるなど、相手を同等の人間と見ることができなかったのである。今抱いている私たちの価値観がどれだけ普遍性が持ち得るのか、実は何も検証していないのである。
17、美(快・不快)の判断とはどういうことか
リスク評価の中に美的な判断などという非科学的な評価を持ち込むのは論外であるというのがリスク評価関係者の大方の考えだと思う。
確かに、芸術至上主義的に、美的判断がリスク評価の最終判断となることは問題だろう。しかし、美的判断というものをバカにはできない。なぜなら、美的判断には、(常とは言わないが)原初的、直感的に本質を捉える場合があるからである。
例えば、多くの市民たちが、なぜ、あれほどまでに強く、遺伝子組換え食品に反発するのか--ひとつには、遺伝子組換え食品に対し、彼らはごく素朴に、何かおぞましい、得体の知れない「不快」な感情を抱かずにはおれないからである。これは厳密なバイオ技術の理解に立脚したものではないとしても、遺伝子組換え技術が、従来の品種改良技術とは断絶した、種の壁を強引に突破する力業であることを知ったとき、生命現象に対するその強引な介入行為に対し、同じ生命体として、思わず、おぞましく、許し難い「不快」な感情がわき上がってくるとしたら、それは十分理に適ったことであり、リスク評価の最初の一歩として極めて貴重なものではないかと思う。これがリスク評価の美(快・不快)的判断である。
また、狂牛病でのたうち回り狂死に至った牛の映像を見た市民たちが、これは「これまでの病気のイメージ」とは隔絶した、生命体が罹るべき病気の限界を越えたとしか思えないような、何か、悪魔に呪われているのではないかと思わずにおれないような、思わず、おぞましく、許し難い「不快」な感情がわき上がってくるのを押えられないとしたら、それもまた十分理に適ったことであり、その判断が検査方法として様々な検出限界を指摘され、検査費用もかさむと散々ケチがつけられたにもかかわらず、利害打算を超えて、全頭検査が多くの市民に支持された根拠になっていたと思われる。これもまたリスク評価の美(快・不快)的判断というものである。
むろん、これまでも、リスク評価の場で、こうした市民の声は暗黙のうちに反映されていた。しかし、それはあくまでも「科学的評価」というリスク評価の正式な判断手続の外野席で、こっそりと取り上げられ(尤も、大抵は無視され)てきた。しかし、リスク評価の「解き方」によれば、こうした市民の声はリスク評価の手続の真っ只中で正面から取り上げられるべき事柄であり、それこそが正しい「解き方」である。
18、リスク評価の判断者とは誰か
以上から、リスク評価の正しい「解き方」によれば、誰が判断者として相応しいかも自ずと明らかだろう。
これまでリスク評価は専門家=科学者がやるものと相場が決まっていた。しかし、リスク評価の本質は科学の問題ではなく、その限界の問題である。ところで、科学の問題に通暁している専門家=科学者であっても、その人は必ずしも科学の限界の問題に通暁しているとは限らない。そうだとすると、ここで必要な専門家とは、第一に、科学というシステムの内部で優秀であるような科学者ではなくて、むしろ科学の限界といういわば「科学のメタレベルの問題」或いは数学基礎論に対応するようないわば「科学基礎論の問題」に通暁している者が相応しい。
他方で、リスク評価とは科学の限界を踏まえて、善(倫理・法律)と美(快・不快)の判断を導入して、それらを総合して判断することである。従って、ここで必要な専門家とは、科学者というより、善や美の方面の文化的訓練を受けた別個の専門家が相応しい。そして、ここで美的判断者として相応しいのは別に美学者でも芸術家でもなく、食の安全と安心についてごく普通の良識とセンスを備えた一般市民である。
ただし、善や美の適正な判断は、真(認識)の適正な判断を基礎にして初めて可能となる。そのために、善的判断者や美的判断者は、予め真(認識)の判断を十分正確に理解しておく必要がある。そこで、彼らと前記の科学の限界に通暁した専門家との緊密な連携作業が不可欠となる。であれば、科学の限界に通暁した専門家の側でも、科学の限界について、一般市民に理解可能な言葉でもって語れる能力(しかし、昨今の専門家でこれを備える者を見つけ出すのは至難の技である!)を備えることが必須となる。
19、現代型リスク評価の課題(小括)
もう一度くり返すが、もともとリスク評価の本領は②善(倫理・法・実践)の次元にある。
しかし、そこで適正な対策を実行するためには、その前提として、①真(認識)の次元で、「不確実な事態」という原因の徹底した認識に向うことが不可欠である。ところが、厄介なことにそこで直面するのは科学というより科学の限界の問題である。そこで、①真(認識)の次元を立派にやり遂げるためには、科学の限界に通暁し、かつ真(科学)の文化的訓練を受けた専門家が不可欠である。
しかも、次の段階の善(道徳・法・実践)の検討では、改めて、その方面の文化的訓練を受けた別個の専門家により行なう必要がある。さらに、真(科学的認識)の判断を基礎にして初めて善の適正な判断が可能となるのであって、そのためには、彼らも予め真(科学的認識)の判断を十分正確に理解しておく必要がある。
したがって、これを一人二役でこなすことは実際上不可能である。そこで、リスク評価には少なくとも上述の2種類の専門家同士の緊密な協働作業(=ネットワーク)が必要不可欠である。
以上から、とりわけ現代型リスク評価(「不確実な事態」をその当時の科学水準に照らし、その危険性を科学的に予測することが不可能なケース)において大切なことだが、リスク評価の急務とは、
①.リスク評価の正しい「解き方」に基いてシステムと評価方法を再構築することであり、
②.科学の限界に通じ、一般市民に理解可能な言葉でもって語れる専門家=科学者を育成すること
である。後者の実現のためには、従来の、異業種交流といっても所詮同業者(科学者)内部の交流でしかないシステムでは全く使い物にならない。改めて、近代科学の祖デカルトが実行した原点に戻り、食の安全と安心についてごく普通の良識とセンスを備えた一般市民=「世間」という大きな書物と交流し、そこから学び直す新たなシステムが作り上げられなければならない。
20、法律家にとってのリスク評価1(食の安全と職の安全)
2007年夏、私は日本弁護士会連合の夏季消費者セミナーに初めて参加し、そこで、食品安全委員会の人に初めて話を聞く機会があり、リスク評価を行う食品安全委員会には法律家の委員が皆無だと知った。言うまでもなくリスク評価は純然たる科学的評価などではなく、あくまでそれを踏まえた政策的価値判断である。だとすれば、ここは真理探求を本業とする科学者より、事実認定を踏まえた法的価値判断のプロである法律家が本領を発揮すべき場である。にもかかわらず、法律家が皆無なのはなぜなのか。食品安全委員会が法律家を敬遠するのは理解できるとしても、「それはおかしい」という声が法律家の側で上がらないのはなぜか。
ひょっとして、法律家はリスク評価の取組みを敬して遠ざけているのではないか。2005年の狂牛病に端を発した米国牛肉輸入問題ひとつ取っても、「真理と政策」のはざまで揺れ動く食品安全委員会の科学者の委員たちの狼狽ぶり、混迷ぶりが明らかであり、こんなぶざまな真似を反復したくないと密かに思っているのではないか。確かにこれらの科学者たちは、食の安全のリスク評価に直面して、翻弄されているように見える。しかし、なぜ彼らが翻弄されるのか。もちろん彼らに対して自分たちの科学研究の財布の紐を握っている国・産業界からの有形無形のプレッシャーがあるからだろう。しかし原因はそれだけではない。狂牛病のようなリスク評価は、科学の力が尽きたところで、この「不確実な事態」をどう評価するのかという判断が問われているからである。それは科学の限界に関する問題であり、科学者が翻弄されるのは当然である。しかし科学者の翻弄を法律家は対岸の火事として済ますことはできない。なぜなら、純然たる科学的認識ではなく、社会の対立する様々な諸価値の調整を最終任務とするリスク評価は本来、価値の調整を任務とする法律家のような者たちの職責だからである。法律家が伝統的な職の安全に立てこもることはもはや許されない。
とはいえ、リスク評価は法律家にとっても鬼門である。なぜなら、リスク評価もまた科学者以上に法律家の正体を情け容赦なく暴くからである。前に紹介した遺伝子組換えイネの野外実験の差止裁判(仮処分手続)の二審で、2005年10月、東京高等裁判所は、組換えイネが作り出すタンパク質(ディフェンシン)が「仮に外部に大量に流出しても耐性菌が出現する可能性は低い」と耐性菌出現の可能性を認め、にもかかわらず住民側の耐性菌の危険性の主張は「杞憂」であると断じた。また、実験の承認申請書に導入する遺伝子をコマツナ由来と書くべきところ、別の植物(カラシナ)由来と記載した事実を認め、にもかかわらず、その事実は承認手続の重大な瑕疵とは言えないと判断した。それはこれを読んだ科学者たちを唖然とさせた[9]。裁判所は「カラシナもコマツナも同じアブラナ科植物で、そのディフェンシンのアミノ酸配列はちょっとした違いだから、その程度のちがいなら実験の承認にとって別にたいした問題ではない」と考えたと思われる。しかし、タンパク質を構成する1個のアミノ酸配列の違いがタンパク質の作用効果に大きな違いをもたらすことがあるのは本GMイネの開発者も認める分子生物学の常識である。しかし、裁判官は、耐性菌出現の可能性も組換え作物が作り出すタンパク質のちがいの問題についてもろくに理解しないまま科学的事実を認定し、今のところ「危険性を示すデータが検出されていない」だから、「判らないけど、ま、いいか」と実験の法的評価を、つまり実験を許容したふしがある。それが科学者の厳しい批判にさらされたのは当然である。
法律家は対立する価値を調整し、一見尤もな法解釈技術を駆使するプロかもしれない。しかし、その前提として目の前に起きている科学的事実を正しく認識できないのならその価値はゼロにひとしい。ましてや、この時「危険性を示すデータが検出されていない限り安全である」といった俗論に逃げ込むのは最悪である。認識なき価値判断は空虚である。法律家にとっても試練の時はすぐそこである。
21、法律家にとってのリスク評価2(法律家の戸惑いの告白)
法律家にとってリスク評価は躓きの石みたいなものである。
法律家が「リスク評価」に躓く理由は1つには、それが科学に基づくものだからだろう。というのは、法律は何を隠そう、世の中の多種多様な専門分野の中でも最も科学から遠ざかった分野だから。文学でさえ、ピアジェの構造主義やチョムスキーの生成文法、ヤコブソンの構造主義的言語学などの一流の科学的研究の成果を踏まえているのに、法律にはそれすらない(構造主義的法律学すらまだ登場していない。その昔、川島武宜が「科学としての法律学」に挑戦したが、それも彼だけで途切れてしまった)。
数年前の夏、法律の最先端分野と言われる特許法を精読したが、発明の機械的、形式的な把握の仕方というレベルの低さに唖然とした。こんな機械的な発想では、最先端の科学や技術の成果である発明の本質にとても肉薄できないだろう、それができないようではいくら法律的な議論を深めていったところで不毛でしかない、と法律の先行きを考えて暗澹たる気持ちにすらなった。
もう1つ、私には個人的な思い込みがあって科学に躓く傾向があった――科学とはもともといかがわしいものである、と。小学校3年生のとき、クラスの女の子から「1+1は?」というトンチクイズを出され、「2だ」と答えると、彼女に「ブブゥ、残念でした。答えは1です」きょとんとする私に向かって彼女は言い放った。「だって、1個の粘土にもう1個の粘土を足してごらん。粘土は1個よ」これ以上完璧な答えはなかった。私は言葉を失った。以来、学校で教える科学と称する学問は、それは単にテストで○をもらうための方便でしかなく、科学は真理とは無縁のものであるというのが私のひそかな確信となった。
しかし、にもかかわらず、私は、現在、科学以上に信頼を置いている分野はない。それは、科学が時と場合によっていかにいかがわしさと隣合せのものであろうが、それがいかにまだ未解明なものを数多く抱えていようが、要するに、ごまんと様々な欠点を抱えていようが、にもかかわらず、それらを上回るただ1つの長所を持っていると思えるからだ。それが「証明」である。つまり、或る命題が証明されていない限り、科学はその命題の存在を主張することは許されないとしていることだ。それは権威や多数決を否定することである。そのことを教えてくれたのが数学者遠山啓であり、言語学者チョムスキーだった。遠山啓によれば、直角三角形に関するピタゴラスの定理は、経験的には古代エジプトで明らかであったが、古代ギリシャが要求したものは、それを真実であると主張するためには証明することであった。古代エジプトのように、王の権威でもってこれを真実とせよと命ずることを認めなかった。あくまでも証明が求められ、その結果、どこの馬の骨か分からないような人物(ピタゴラス)でも、それを証明し得た以上、受け入れられた。
この証明の精神こそ、過去、現在、未来にわたり科学が信頼を持ち得る殆ど唯一の基準のように思える。
ところが、今はやりの「リスク評価」は、この証明精神を骨抜きにするための、いかがわしさに満ち溢れているのではないかと思うことがある。なぜなら、証明とは、本来、或る命題を積極的に証明することであるのに対し、その反対の命題が証明されていないことを持って、こと足れりとするようなロジックがまかり通っているからだ。例えば、遺伝子組換え生物が外界に及ぼす危険性について、本来であれば、「そのような危険性がないこと」について証明してみせるのが科学である。しかし、世の中で往々にまかり通っているのは、上の命題の反対の命題「そのような危険性があること」を持ち出して、その命題を根拠づけるデータが今のところ示されていないことをもって、「そのような危険性があること」は今のところ証明されていない、だから、「そのような危険性がないこと」と考えてよいという結論、或いはそのような結論を前提にした対策が導かれていることである。これは、あたかもピタゴラスの定理について、「直角三角形の2辺の2乗の和は、斜辺の2乗にひとしい」とは限らないという命題が今のところ証明されていない以上、「直角三角形の2辺の2乗の和は、斜辺の2乗にひとしい」という命題が証明されたと考えてよいというのと同様である。
これはインチキではないか。なぜなら、証明とは元来、その命題を積極的に証明することであって、その反対命題を成立しないことを暫定的、消極的に示しただけでは足りないのは明らかだからだ。
しかし、こうしたインチキが堂々とまかり通っているのを見ると、これは確信犯ではないかとすら思う。つまり、「リスク評価」は科学に基づく必要はなく、単に科学に基づいているように見せかけることができさえすればよいのだ、と。言い換えれば、「リスク評価」は偽装科学が活躍する舞台だ、と。
しかし、これは何も特別なことではない。マキアヴェベリは、君主論で、君主は聖人である必要はないが、そう見える必要があるということを言っている。それと同じことだからだ。つまり、「リスク評価」もまた科学に基づく必要がないが、そう見える必要がある、そして、それ以上でもそれ以下でもない、と。
その意味で、「リスク評価」はマキアヴェベリの「君主論」と同じで、本質的に「政治」の領域の問題である。もっと言えば、マキアヴェベリの「君主論」が、いかにして大衆の支持を獲得するかという「広告」の問題であるのと同様、「リスク評価」もまた、いかにして大衆の支持を獲得するかという「広告」の問題である。
それゆえ、「リスク評価」を有効に分析し、批判するためには、科学者や法律家というより、マキアヴェベリのような冷徹な政治批評家や広告批評家の才能と力量が求められる。もちろん、この指摘自体が、現在「リスク評価」を推進している人たちにとって容認しがたいことだろう。しかし、今まず必要なことは、「リスク評価」のやり方はいかにあるべきかを問うことではなく、現在進行中の「リスク評価」の正体の科学的分析である。それが適正に科学的に分析されれば、そこで、きっと「政治」であり、「広告」であることが明らかにされるであろう。
つまり、まずは、「リスク評価」が科学であることをまとった「政治」であり、「広告」であることことを知らせないことを止めて、科学であることをまとった「政治」であり、「広告」であることことを科学的に証明した上で情報公開すべきである。
その上で、科学であることをまとった「政治」であり、「広告」である「リスク評価」を、では、どうしたら、よりまともな「政治」であり、「広告」として機能し得るようになるのか、という課題に初めて正面から取り組むことが可能になるだろう。ここでもまた、私は、科学的精神のエッセンスである「証明」が最大の武器になり得ると思う。但し、今度は、「リスク評価」が対象としている遺伝子組換え生物といった不確実な現象だけではなく、それらの開発をめぐる有象無象の利害関係人の利害衝突という魑魅魍魎とした不可解な現象の「証明」である。その意味で、科学的精神の「証明」が活躍する出番はまだまだ無尽蔵にあり、新たなに「政治」の科学者、「広告」の科学者の出番も無尽蔵にある。この意味で、法律家の私に「法律」の科学者として何ができるのか、「リスク評価」を通じて、突き付けられ続けている。
以 上
[1] これに対する私の解は、法律至上主義の検察の立場でも、芸術至上主義の澁澤の立場でもなく、――美のことはまず美に聞け。それから、善の判断に進め、というものである。
[2] http://song-deborah.com/copycase/
[3] http://www.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/29-3.html
[4] http://www.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/30-3.html
[5] 以上AからFまでの分析は、柄谷行人「倫理21」(平凡社)〔第四章 自然的・社会的因果性を括弧に入れる〕の記述に拠ったものである。
[6] もし実損害が100万円で、心証度が80%なら80万円の損害を認め、心証度が40%なら40万円の損害を認めることになる。
[7] ≪疎明によれば、本件GMイネによって生産されるディフェンシンがその体外に流出する可能性は低く、仮にディフェンシンが外部に大量流出しても、耐性菌の出現する可能性も低いことが認められる。したがって、抗告人(注:原告市民のこと)らの主張する上記主張は、杞憂であり、理由がない≫(2005年10月12日東京高等裁判所第5民事部の決定3頁)
[8] 事実、植物の遺伝子組換え技術を開発する研究者の中には、植物の苦痛を論じる者もいる(例えば、It should be pointed out that the cloned
CaMV DNA suffered no major insertions or deletions during reintroduction into
the plant.[Howell Stephen H])。
[9]平成17年10月12日の東京高等裁判所の決定を読んで(http://ine-saiban.com/saiban/voice-pro.htm)